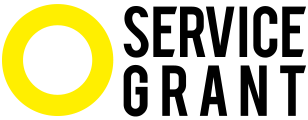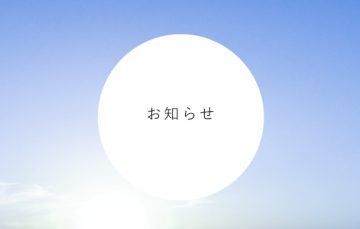サービスグラントは2025年1月に活動開始から20周年を迎えました。
同年3月末をもって、代表理事の嵯峨生馬が退任し、代表理事2名による共同代表制へと移行します。職員の互選により信任された運営委員と共同代表が中心となり、理事及び職員全員での自律的・主体的な組織運営に取り組んでいきます。詳しくはこちら
NPO法が設立してから26年あまり。サービスグラントのみならず、NPOの事業承継について耳にすることが増えています。
サービスグラントの活動初期の頃から関わりのある、認定NPO法人マドレボニータのファウンダー/前代表理事で、現在はNPO法人シングルマザーズシスターフッドの代表理事である吉岡マコさんにお時間を頂き、事業承継をめぐる想いについて、対談の機会をいただきました。

一人ひとりが自律的に力を発揮できる組織づくりと事業承継のプロセス
嵯峨:サービスグラントでは、2025年3月末に私が代表理事から退任し、4月からは岡本祥公子、槇野吉晃による共同代表制となります。マドレボニータと似ていますよね。参考にさせていただいた部分が多々ありました。
吉岡さん:確かに、マドレボニータも私の退任後は共同代表制となりました。 立候補してくれた6人が理事となり、定期的にアドバイザリーボードとして外部の方も関わってくださっています。今は、私の方はシングルマザーズシスターフッドの運営に注力しています。
嵯峨:サービスグラントでは、これから、2人の代表理事とともに、運営委員というメンバーが組織運営を担っていきます。運営委員は、立候補の上、職員全員による信任投票を経て4名。共同代表の2名とあわせて計6名が「運営ユニット」としてコアを担いながら、メンバー全員に運営をひろげていくかたちです。サービスグラントの場合は、理事がマドレボニータさんのアドバイザリーのような位置づけとなっています。
吉岡さん:サービスグラントは運営をはじめてから何年になるのでしたっけ?
嵯峨:ちょうど今年で20年となりました。
吉岡さん:長いと言えば長いですよね。PTA会長や町会長で20年もやる人はなかなかいないですし(笑)
嵯峨:そうですね。代表交代については、数年前からポロポロと話題にだしていました。岡本さんに、ティール組織の研修に連れていかれたりもして。行ってみると、じわじわと、なるほどと思う部分が増えていきました。フラット、という言葉では単純すぎますし、絶対的な正解と言えるような型があるわけでもない、ただ、ピラミッド型の潮時を感じたなかでは、選択肢としてこれしかない、と思うようになりました。
吉岡さん:ティール組織を表現するのは難しいですよね。ミスリーディングになることもあったり。
嵯峨:もともとサービスグラントの活動は私がひとりでスタートしました。そこにふらっと現れた岡本さんが加わって2人の組織になり、年々事務局メンバーが増えて10人に近づいたころから、情報共有の難しさが発生し、マネジメント体制をちゃんとつくらなければ、という意識が強くなりました。代表が決める、事務局だけで頑張る、というところから、変えなければいけない。失敗や教訓を通じて、私自身学んでいったところがありました。
吉岡さん:やらないと分からない、やりながら形になっていくところもありますよね。
嵯峨:2015年あたりからは、プロボノワーカーの中でもコアな人たちに、正会員になってもらい、運営に関する議決権をもちながら「パートナー」としてプロボノプロジェクトの団体審査と採択を共に担ってもらう、ということをはじめました。そのあたりから、プロボノワーカーのみなさんも、ただ参加するだけでなく、自分たちでやっていく、という感覚ができていったと思います。
事務局長というポジションで小林さんが立ってくれたのですが、2020年ころには事務局メンバーが30名規模になり、事務局長と代表だけで運営をなんとかする、というのでは回らない。主体性をどうみんなが持てるか、ティールの視点をもっと入れよう、となった流れでした。
そこで、「運営ユニット」というのを2年ほど試行実施し、正式にかたちに出来そうだと感じたころ、同時に自分の潮時を感じたこともあり、一度リセットする形で次の体制に移るのはどうか、という考え方になりました。
吉岡さん:組織運営は、アートと言ってもいい領域ですから、難しいですよね。時間をかけてつくってこられたからこそ、代表交代も「そろそろかな」と思うことができたのですね。
嵯峨:そうですね。このメンバーなら大丈夫だろう、サービスグラントとして培ってきたものを支えるのには、自分が続けていくよりいいかたちになるだろう、と思えました。

吉岡さん:組織が大切にしている価値観やバリューを共有できているという安心感はあったのでしょうか。
嵯峨:サービスグラントは活動初期の時代、「do it pro bono.」を掲げていました。ただ、プロボノは一つの手法で、コアなものでありながらもその先にあるものを見つめていかなければならないという危機感もありました。2015は転換点。「社会参加先進国へ」というビジョンと、「プロボノを進化させる」というミッションを掲げました。「課題先進国」という言葉は当時もありましたが、もう一歩建設的なものにしようと考えるとこのことばに行き当たりました。理事や身近な人たちに最初に提案したときは、ちょっとざわつくような「何それ」みたいなコメントもありました(笑)。その状況も悪くないのではと思って振り切ったかたちでしたが、10年経った今でも、まだ十分に新鮮だと思うときもあれば、手あかがついてきたと感じる瞬間もあります。
いま、事務局メンバーで、ビジョンの整理も始まっています。新たなビジョンを掲げてもいいと思う一方で、この先も、自分の考えが意識されてしまうところもあるんだろうなと思ったりもします。そこは気にせず、新しい方向に全力で振り切ってほしい、と、私自身は思っています。
吉岡さん:代表を尊重するのもいいけど、頼りすぎ、任せすぎてしまうというのはどうしても起こりがちなように感じます。現場を知っているからこそ見えるものがあり、それを知っているメンバー自身が、自分たちの目線で考えることも大切ですよね。
嵯峨:代表というのは、良くも悪くも矢面に立つ存在。代表じゃないと出来ないこと、責任者が必要なシーンもあります。見える景色も違うかもしれません。新しい代表がどんな景色を見るのか、また、メンバー一人ひとりがそれぞれの視点を活かして、どの方向にアクセルを踏んで展開していくのか、とても楽しみです。
吉岡さん:新代表を決めるにあたってはどのようなプロセスだったのでしょうか?
嵯峨:1人よりは、2人、多くて3人かな、などと思っていました。
吉岡さん:かものはしプロジェクトさんも、一時期は3名でされていましたよね。
嵯峨:個性のバランスも考えて自分から直接依頼をし、最終的には岡本さん、槇野さんの二人に担ってもらうことになりました。突破力や勢いのある岡本さんに加え、関西事務局で長く勤めている槇野さんは、その距離をもってしてもよく観察をしてくれている。独断に近いかたちにはなってしまいましたが、最初のバトンは私から渡そうと、このようにしました。
吉岡さん:広げる、まとめる、ですね。他のみなさんのリアクションはどうでしたか?
嵯峨:退任に対して不安、という声もやはりありましたが、新たな体制について楽しみに感じてくれている人がとても多かったですね。
吉岡さん:みなさん、心の準備はできていたんですね。正会員や他のステークホルダーの方々はどうでしたか?
嵯峨:代表退任とあわせて、新たな運営体制も発表しました。反発はなく、受け入れてもらえたかと思います。
吉岡さん:マドレでは、正会員が多いこともあり、複数回に渡って説明会をしました。新代表、新理事メンバーにもスピーチしてもらったのですが、回を重ねるごと にどんどん覚悟が決まっていくのか、スピーチもブラッシュアップされていったことに感動したのを覚えています。 代表交代についても、立候補制にしたい、と思って説明と対話を重ねました。内部の人はそんなに驚かなかったのですが、外部の人の方がびっくりしたり、寂しがってくれたりもしました。短期間に起きた大きな変化でしたが、時間をかけて対応していきました。
マドレはみんなのもの。一人一人がリーダーシップを発揮していこうというのは、サクセッションを考える前からやって来ていました。なので、「こんどは私たちの番だ」というのは感じてもらえていた気がします。残念ながら、去っていった方もいたのですが、「マドレが無くなるのはいやだ」と感じてこの変化を引き受けてくれた人、ポジティブにとらえて応援してくれた人も多くいました。言い出してから退くまではちょうど半年くらいでしたが、当時マドレボニータの監事だった岡本拓也さんには、よく相談していましたね。
嵯峨:吉岡さんは、退任されて以降は関わっていらっしゃるのですか?
吉岡さん:一切関わっていない状況です。ただ、創業者という名前はあります。ときどきインフォーマルに連絡を取っていますが、正式なかたちでアドバイザリーをしていたりということはないです。
嵯峨:そうなんですね。私は、決算月である9月までを目途に、代表退任後から半年程度は移行期間としてフォローアップをしたり、講師として講座に入ることはあるかな、と思っています。
吉岡さん:やってみてからですよね。半年ってあっという間。
嵯峨:岡本さんは「サービスグラントの新たな側面を出さなければ」と、前向きな危機感を言葉にしてくれています。
吉岡さん:マドレでも、新体制への移行にあたってはやっぱり危機感はあって、でも、だからこそ、出せるだけの力を全員が発揮していると聞いています。私のこだわりは初期から明文化していたのですが、一緒にやってきた仲間は、私以上にそのこだわりを共有し、体現してくれていました。例えば「参加者をママと呼ばない」といったことは、DNAとして受け継がれています。ただ、その柔軟性、時代に併せて進化していった方がいい点は、信頼して見守って います。
嵯峨:新しいものは生まれてきていますか?
吉岡さん:東京マラソンのチャリティー団体として採択され、「産後ケア×ランニング」を新しいエンパワーの形にとして打ち出していたり、NIKE社内のボランティアチーム”Women of Nike and Friends Japan”の皆さんとコラボイベントを開催したり、新しいことに次々と挑戦していっているようです。コロナ禍の時もいろいろと悩みながらも、チャレンジしていました。

嵯峨:マドレボニータさんを見ていて、白書はいいなと感じました。サービスグラントでも今、白書を作ろうとする動きがあります。
吉岡さん:マドレボニータでは、産後ケアの大切さを、当事者にはわかってもらえるのですが、それ以外の人になかなか理解されないという現実を受けて、「産後ケアの大切さ」を上手く伝えるためにどうしようか、アンケートをデータとして示すことができれば説得する材料ができるのでは、と白書の制作が始まりました。 厚生労働省の調査では、産後うつは11人に1人、とあったのですが、そんなわけはないだろう(もっと多いはずだ)、と自分たちで調べました。診断されていないけどうつ症状があった人も調べてみると8割くらいに上りました。その後、政策ができるまでの流れの中で政府の会議などに正式に呼んでもらえることはなかったのですが、リアルなデータを提供したことは大きな貢献だと思っています。
嵯峨:サービスグラントとしては、どんなデータをとることが貢献につながるだろうかと、今後の動きに期待したいなと思っています。
吉岡さん:嵯峨さんは、退任後はどうされるのですか?
嵯峨:これまでなかなか時間をとることが難しかったことをやってみたく、まずは執筆に手を付けようかと思っています。他にも、思い切って新たな地で、新しいことにチャレンジしてみようかなと計画中です。
吉岡さん:私は、マドレを退任した後、休む間もなく シングルマザーズシスターフッドを立ち上げました。勢いで4年間走ってきましたが、息切れしないようにもう少し続けていきたいと思っています。
嵯峨:サービスグラントでは「ふるさとプロボノ」というプログラムも行っているのですが、もともと私自身、農とか、農山漁村には関心があったんですよね。「ふるさとプロボノ」は、地方創生と関係人口創出などを目的に実施してきたわけですが、人口減少の大きな課題を前に、まだまだわからないことも多く、現場に身を置いてみる、ということからどんなことを感じ取れるのか・・・。今はそんな気持ちです。
プロボノの広がりと、ソーシャルを取り巻く変化
吉岡さん:嵯峨さんが活動をはじめた当初は、プロボノという言葉も通じなかったですよね。先日企業が主催するイベントに行ったら、プロボノをする人が160人くらい集まっていて、すごいな、と驚きました。企業としても推進したい、若い社員としてはイケてるアクティビティと捉えられるようにもなっているのではないでしょうか。
嵯峨:ソーシャル界隈もにぎやかになってきていますよね。
吉岡さん:今は、スタートアップが流行っていて、一時よりNPOが少し勢いをなくしているのではないか、というのも気になっています。
嵯峨:一般社団法人が大きくなってきたことも影響していますね。
吉岡さん:私は公共性の視点でも絶対にNPO法人がいい と思ってシングルマザーズシスターフッドも法人格はNPOを選び ました。アメリカでは、NPO がすごい数ありますよね。例えばマサチューセッツ州では、人口が東京の半分なのにNPOが東京の2倍あります。街のそこら中でチャリティー活動が行われている。 そこに関わっている人たちも、みんなカッコよくて、カルチャーショックを受けました。
嵯峨:フランスで活動するPro Bono Labという団体が最近「Democritize Pro Bono(プロボノを民主化する)」というコンセプトを掲げるようになりました。大企業だけがプロボノをするのではなく、中小企業や大学などにプロボノを広げていきたい、という大きな戦略転換です。ソーシャル全体に新しい人の流れが生まれてきているなかで、サービスグラントは大企業のプロボノにおいて、それ以外の分野において、どう動いていけるのか、ですね。
大事なところは、どのような方向に進むにせよ、すそ野を広げることであり、質の高いプロボノをいかに広げるか、にあります。サービスグラントが、社会参加プラットフォーム「GRANT」を立ち上げたのも、そうした機運が高まってきたからこそでした。
吉岡さん:シングルマザーズシスターフッドも、「GRANT」に団体登録しました。
嵯峨:今振り返っても、「GRANT」を立ち上げたことは大きかったと思います。2018年に年間のプロボノプロジェクトが100件を超えて、その年の年次報告書に、次は1,000件を目指そう、と書いたのが始まりでした。ニーズや潜在的な可能性は十分にあります。ただ、この規模感を実現するには、やり方のイノベーションが必要でした。先行してアメリカのTaproot Foundationでの仕組みがあったので、それをヒントに、日本での展開の構想を練っていきました。サービスグラントとしてのこだわりを、文章における問いかけ方などに込めました。100%とまではいきませんが、かなりの高い確率でプロボノ参加者と団体とがつながる流れができてきました。今課題なのはコーディネーターの役割です。
吉岡さん:なかなか難しい役割になりますね。団体と支援者がいるだけでもだめですし、プレイヤーがまだまだ少ない。海外では、プロボノに助成金がでたり、プロボノをやった分の給料が払われるマッチングの寄付などがありますよね。日本ではまだほとんどないですよね。
嵯峨:コーディネーターがやはり足りないのかもしれないですね。海外では、プロボノコーディネートの経験をアピールポイントとして企業で働いている人もいると聞きます。
吉岡さん:1社に2~3人、ソーシャル領域とのコミュニケーターがいるといいですよね。
嵯峨:まさに、サービスグラントのプロボノワーカーの方々がその走りとして活躍してもらえそうですね。一昨年から、「社会参加オープナー」という資格をつくって、新しい人を巻き込みながらコーディネーターを増やそうともしています。
吉岡さん:コーディネーターの重要性が理解されてきている様子は感じます。課題を共有するのにもコツがあるなと。サービスグラントはその知見を豊富に持っていらっしゃいますよね。
嵯峨:プロボノが広がっていくなかで、失敗した事例も少し耳にするようになってきました。その経験をいいプロボノの形に塗り替えていくのが私たちの仕事だと思っています。今のサービスグラントのメンバーはオールスターキャスト。すばらしいメンバーがそろっています。常に磨き続けて、妥協せずにやっていって欲しい、と思っています。
吉岡さん:団体のカルチャーとして、そこが生きていくといいですよね。
嵯峨:ツールづくりも大切だけれど、それを動かすのは人や仲間。それぞれがいきいきと活躍していってくれたらいいですね。
(2025年3月)